近年、誰でも簡単に開発ができる「ノーコード」への注目が高まっています。
日本でも活用が広がってきており、具体例をあげると、特別定額給付金申請用のサイトを1週間でリリースした加古川市の事例や、非エンジニアが作った就活向けのオンライン面談マッチングアプリの事例など、行政、民間を問わず直面している課題解決のためにノーコードでの開発を取り入れています。
徐々に普及してきているノーコードですが、「キーワードとして知っているが詳細はわからない」「従来の開発(スクラッチ開発)と比べた時のメリット・デメリットがわからない」「そもそも何に使えるのかもわからない」といった方もまだ多いのではないでしょうか。
本記事では、「ノーコード」の概要、スクラッチ開発と比較した時のメリット・デメリット、活用パターンについて解説します。
ノーコード開発とは
ノーコード(No-Code)開発とは、プログラミングをすることなくアプリケーション、Webサイトなどを開発することです。
一般的に、Webサイトやアプリケーションを開発するには、プログラミング言語を使用してソースコードを書く必要があります。しかし、ノーコードでは専用のツール(ノーコードツール)を使うことで、非エンジニアでもソースコードを書くことなく開発ができます。
ノーコードツールとはどのようなものか
ノーコードに使用するツール(ノーコードツール)は、非エンジニアでも直感的に開発をすることができるように設計されています。
ノーコードツールには、Webサイトやアプリケーションを開発するのに必要な機能がパーツやテンプレートとして用意されています。それらをGUIでドラッグ&ドロップし組み合わせることで、完成のイメージを見ながら開発することができます。
ノーコードツールには用途に応じてさまざまな種類があります。
代表的なものはWebアプリケーション開発に特化した「Bubble」、モバイルアプリケーション開発に特化した「Adalo」、ECサイト構築に特化した「Shopify」、Webサイト構築に特化した「WordPress」や「Wix」などがあります。
ちなみに、本サイトには「Bubble」を使用しています。
ノーコードのメリット
ノーコードでの開発(ノーコードツールを用いた開発)は、スクラッチ開発と比較して以下の3つのメリットがあります。
開発の工数を削減できる
ノーコードではWebサイトやアプリケーションの開発において「コードを書く」という作業工程を大幅に削減することができます。
また、従来の開発ではWebサイトやアプリケーションを実行する環境を別途用意しなければならない場合もありますが、多くのノーコードツールではその環境も提供されているため、「サービス提供環境の整備」にかかる工数も削減することができます。
その結果、リリースまでのスピードが非常に速いです。
どのくらい早くなるかというと下図のように、スクラッチ開発にかかる半分の期間でアプリケーションを開発・テストすることができます。(当社調べ)
さらに、「コードを書く」ことや「サービス提供環境の整備」にかかっていた時間や人的リソースをそのほかの重要事項(サービスの設計やUXデザインなど)の検討に使うことができるようになります。
非エンジニアでも開発できる
スクラッチ開発の場合、社内のシステム部門や外部ベンダーに依頼する必要があるので、多くの時間と費用がかかります。
また、仮にプログラミングできる人を新たに雇おうとしても、IT人材不足という社会的な課題があるため、採用は簡単ではありません。
ノーコードであれば、ツールに備わっている機能や使い方さえ覚えれば誰でも開発することができるので、プログラミングの知識がない職種(営業、事務、経理、人事など)の人でも簡単にWebサイトやアプリケーションを作ることができます。
導入費用が安い
ノーコードツールは他のクラウドサービスと同じく、導入費用が安いです。
無料プランから使えるものも多く、有料でも月額数千円〜数万円で利用可能です。
例えば、新規サービスのプロトタイプをスクラッチ開発で作るとも数百万円の費用がかかるようなケースでも、ノーコードであれば数万円から始められる可能性があります。
開発の内容によっては無料で試しに使ってみて、合うようなら有料のプランに変更、合わなければ別のツール(あるいはやり方)に変更するという判断も可能です。
ノーコードのデメリット
誰でも、素早く、導入コストを抑えた開発ができるノーコードですが、「ツールへの依存度が高い」ことから、スクラッチ開発と比較して以下のようなデメリットもあります。
ここではノーコードの導入を検討している方に向けて、デメリットに対しての備え・対策とともにご紹介します。
できることが決まっている
ノーコードツールはどれも基本機能に加えて、豊富なオプション機能やAPIを備えているため、幅広い要望に対応することができますが、スクラッチ開発ほどの自由度があるわけではありません。提供されている機能でできることであれば迅速かつ柔軟に対応できますが、機能として備わっていないことには対応できません。
どういった結果を得たいのかなど目的を明確にして要件定義し、導入の対象となるツールで提供されている機能で実現可能かどうかを照合しておく必要があります。
また、導入したツールで対応できないことが起きた場合どうするかをあらかじめ決めておくことです。状況や目的に応じて、別のツールに切り替えるのか、今あるものをベースにスクラッチ開発を行うのか、あるいは対応できない部分についてだけ運用で補うのか判断をする必要があります。
セキュリティが提供ツールの環境に依存する
ノーコードに限らずクラウドサービスのセキュリティは提供されている環境に依存します。
そのため、ツールの提供会社が自社の求めるセキュリティレベルを満たしているか確認する必要があります。例えば国際認証であるISO 27001/ISO 27017認証やPCI DSSを取得しているか、GDPRに対応しているか、などを確認しましょう。
また、ノーコードツールで開発したサービスを社外へ提供するような場合については、ツールで提供されるセキュリティ機能についても検討する必要があります。
導入を検討しているツールの機能で、提供しようとしているサービスで定めたセキュリティ要件を満たすことができるのか確認し、導入後には確実に設定をする必要があります。
サービスが提供終了した場合の移行が困難
これもクラウドサービス全般で起こりうることですが、ノーコードツールでの「サービス終了」には一般的なパッケージサービスの利用とは異なり、移行や乗り換えが困難な場合があります。
社内向けのシステムで利用している場合については近しい機能をもつサービスがあれば、乗り換えを検討することもできると思います。しかし、そのほかのシステムとの連携や運用については見直しが必要になる可能性があります。
また、社外へ提供するプロダクトを構築・運用している場合は、どのようにそのサービスを継続させるのかを検討しなければなりません。近しい機能を提供している他のツールで新たに構築するにしても、スクラッチ開発に移行するにしても、かなりの工数と費用がかかります。移行に必要なコストと、サービスの収益を比較した時に事業そのものを停止するという判断をしなければならない場合もあるでしょう。
事前にできる対策としては、ツール選定の時に、「ツールの提供継続が見込めるか」と「サービス終了になった場合ソースコードをダウンロードするなどの救済策があるのか」を確認しておくと良いでしょう。
ノーコードの活用パターンとは
ノーコードの概要、メリット、デメリットがわかったところで、「どのように活用するのか」についてご紹介します。
ノーコードでの開発は主に「社外向けに新規サービス開発ツールとして活用する場合」と「社内の業務改善に活用する場合」のようなケースで有効です。
社外向けに新規サービス開発ツールとして活用する場合
例えば、新規サービスを開発する際にMVPやプロトタイプをノーコードで開発する事ができます。
メリットの部分でもお伝えしているとおり、従来の開発手法と比較して開発にかかる工数や導入コストを大幅に削減できます。そのため、限られたリソースを有効に活用し、新規サービスの検証・改善をスピーディーに進めることができます。
社内の業務改善に活用する場合
例えば、人が対応している定型業務の自動化や、申請業務の電子化などについて、ノーコードで開発する事ができます。
ノーコードであれば、ツールの使い方さえ覚えてしまえば誰でも開発ができるため、業務改善が必要な現場で働く非エンジニアが、開発・運用することも可能です。そうする事で、従来であれば時間やコストをかけて外注していた業務改善のためのシステム開発を、社内でコストを抑えて、迅速に開発・改善していく事ができます。
まとめ
ノーコードを使えば「少ない開発工数で」「誰でも」「導入費用を抑えて」Webサイトやアプリケーションを開発することができます。業務効率化のためのシステムの開発や、新規事業開発でのMVP、プロトタイプ開発をするときに非常に役立つ手法だといえます。
しかし、デメリットであげているようにツールへの依存度が高いので、以下3点は導入前に必ず確認する必要があります。
・プロジェクトで必要となる要件を満たす機能があるのか
・セキュリティ対策は問題ないのか
・サービス停止のリスク回避策はあるのか
また、各種プロジェクトでノーコードを導入する前には、以下のようなことも検討しなければなりません。
・MVPやプロトタイピングに利用する場合、どこまで機能で開発を行い、何を検証するか
・業務システムに利用する場合、既存のシステムや業務フローとの連携はどうするのか
・Webサイトやアプリケーションのデザイン設計はどうするのか
・リリース後の運用改善はどう進めていけばいいのか
このような場合には専門的な知識や経験が必要になりますので、多少コストはかかってもアプリケーション開発の経験豊富なエンジニアやコンサルタントを外部から招き入れてアドバイスをもらいながら進めた方がいいでしょう。
NCDCであれば、業務アプリケーションの開発から新規事業立ち上げサポート、リーン・スタートアップ、アジャイル開発の経験も豊富なため、包括的なサポートをさせていただきながら開発をご支援することが可能です。ノーコードの活用を検討されている場合にはぜひご相談ください。


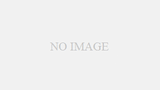

コメント