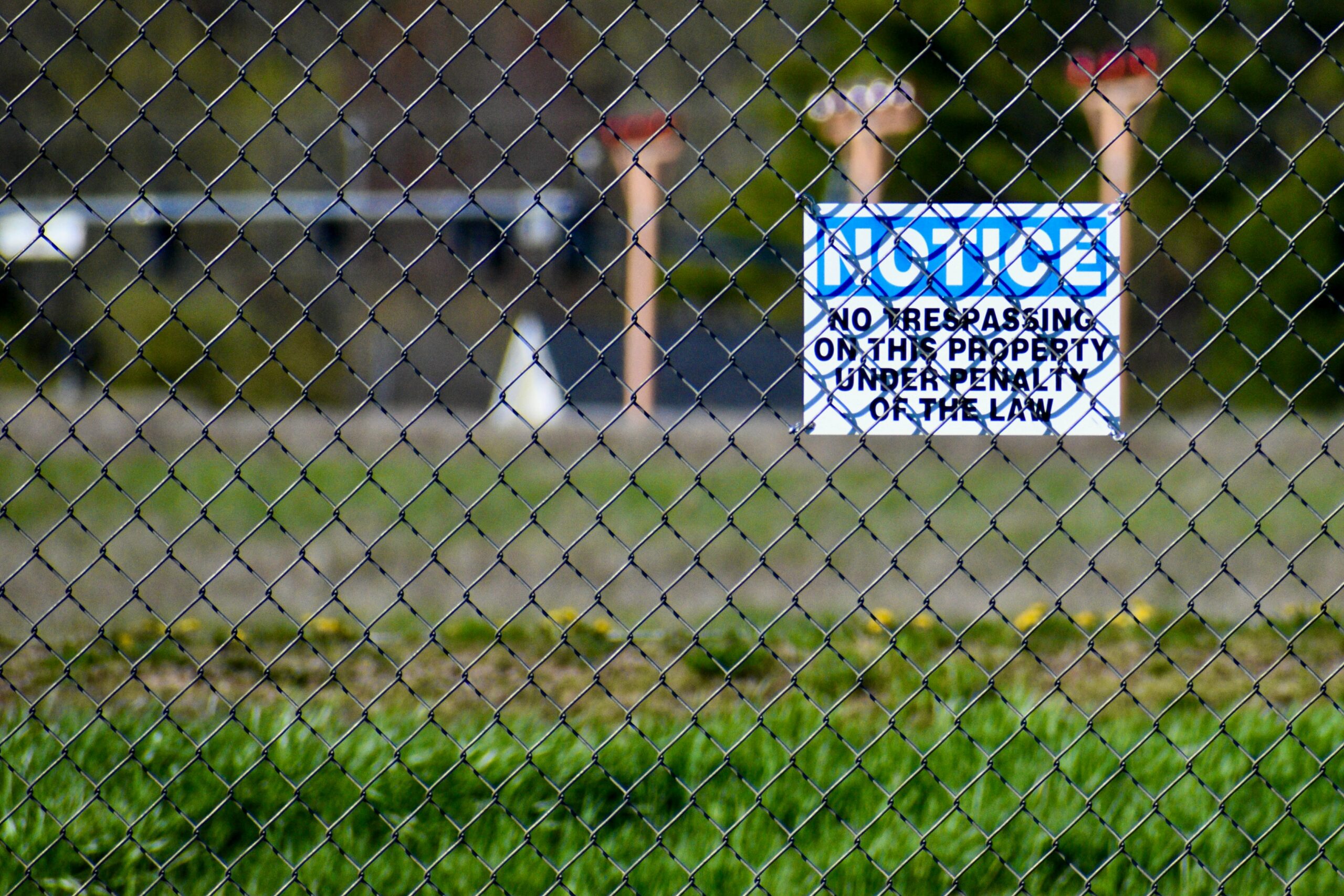プロトタイプ開発とは、システムやアプリケーションを開発する際に、リリース前の早期の段階で実際に動作する試作品(prototype/プロトタイプ)を作り、機能や動作を確認・改善しながらプロダクトを完成させる開発手法のことです。
プロトタイプ開発自体は多くの産業で行われている手法ですが、このコラムではソフトウェア開発におけるプロトタイプ開発について説明していきます。
システムが出来上がってから「これでは使えない」「これではイメージが違う」といった事が起きないようにするためにはプロトタイプ開発は有効な手段です。特にソフトウェアの場合、完成品が目に見えないため、ソフトウェア開発に慣れていない方にとっては齟齬が起きやすいので、完成時のリスクを減らす意味でもプロタイプ開発は有効です。
メリットの多いプロトタイプ開発ですが、具体的にはどのようなタイミングでどんなふうに進めるのでしょうか?
本記事では、プロトタイプ開発を行うタイミングと具体的な進め方、プロトタイプ開発の際に気をつけるべきポイントについてご紹介します。
プロトタイプ開発を行うタイミング
プロトタイプ開発は、プロダクトの有効性を判断したり、仕様を確定するために行います。したがって、試作するタイミングとしては、コンセプト、技術の実現性が確定している上で取り掛かるのが一般的です。
早期に試作品を作成することで、フィードバックを受けながら、その都度軌道修正してシステム開発を行います。そのため不具合や動作不良も早期に発見し改善できるので、後戻りが少なく、結果的に開発効率の向上にも繋がります。
プロトタイプ開発の流れ
具体的なプロトタイプ開発の流れは、「検証内容の定義」「プロトタイプの要件定義」「プロトタイプの設計」「プロトタイプ開発」「評価・判断」の5つのステップで進めていきます。
特に、プロトタイプ開発においては、開発に入る前の「検証内容定義」と「評価・判断」が非常に重要です。目的に合っていないプロトタイプは、検証失敗する可能性が高く、無駄になります。それどころか、プロジェクトメンバーとの認識齟齬を大きくしてしまう可能性もあります。
①検証内容の定義
検証内容は開発予定のプロダクトの性質に大きく依存してきます。完成品のビジネスモデルについての検証とするのか?ユーザーの使用性の検証をしたいのか?技術的リスクを検証したいのか?様々です。
検証内容を定義した後は検証方法の設計も必要になります。Webのアクセスログで取得できるものなのか?使用者のインタビューを行うのか?UXデザインの観察の手法を取り入れるのか?など設計を行います。
そして、最後に検証時のしきい値も設計しておくと良いでしょう。例えばコンバージョン率が3%であればOKとか、はじめて使用するユーザーの80%が迷わずこのページまでたどり着ければOKなどです。
②プロトタイプ要件定義
検証内容に即した機能を具体化し、プロトタイプの開発要件を定義します。
ここでは、「プロトタイプをその後どうするのか?」ということについても決めていくことが非常に重要です。
工業製品のプロトタイプはあくまで「試作」であり、完成版ができたら廃棄をすることになりますが、ソフトウェア開発の場合はプロトタイプを改善し、そのまま完成版としてリリースをするということも技術的には可能です。
捨てるのか、そのまま完成品にするのかによって要件定義の内容や厳密さが変わってきます。かつ、プロトタイプの設計など、後工程にも大きく影響してきます。
サービスの内容や事業計画などにも関わることになるので、事前に判断が必要です。
③設計
②で定められた要件を元に、プロトタイプの設計を行います。
この段階でも、試作は捨てるのか?そのまま完成品とするのかによって設計の厳密さが大きく異なり、工数・期間にも大きく影響がでますので注意が必要です。
④プロトタイプ開発
実際のプロトタイプを開発します。
⑤評価・判断
①で定義した内容に従って検証・評価・判断を行います。
しきい値に達しない場合、どのような対応を取るかは事前に決めておくことも難しいため、ステークホルダと議論が必要になるでしょう。
プロトタイプ開発とノーコード開発
先述しているように、プロトタイプ開発ではプロダクトの完成を目指して評価・修正を繰り返していきます。この部分をスピーディかつ柔軟に実行するにはノーコード開発が適している場合があります。
ノーコード開発とは
ノーコード開発とは、あらかじめ用意されているパーツやテンプレートを画面上で操作し組み合わせることで、直感的にWebサイトやアプリケーションの開発をすることです。
従来の開発手法では必要とされる「コードを記述する」というプロセスを省略することができるため、開発工数を大幅に削減し、素早く柔軟に開発・評価・修正のサイクルを回すことができます。
ただし、ノーコード開発ツールでの開発はサービスで提供されいてる機能やセキュリティ環境への依存が強いため、製品としてリリースをする場合には要件を満たしているかの確認が必要です。そういった点を考慮した上で、適用できそうであればプロトタイプ開発の強い味方になるでしょう。
ノーコード開発について、詳しくはこちらの記事でも紹介しているのでご参照ください。
ノーコードとは?概要、メリット、デメリット、活用パターンについて解説
プロトタイプ開発で気をつけるべき問題点
ここまでで、プロトタイプ開発の流れについては理解できたと思いますが、いざ実施しよう、となると注意しなければならない点もあります。
プロトタイプの作成が目的になってしまう
これは、目的を十分考えないまま見切り発車的にプロトタイプ開発に着手するケースのことです。
プロトタイプはあくまで完成形となるプロダクトの仕様検討や、ブラッシュアップにつなげることを目的としています。プロトタイプ開発そのものを目的としてはいけません。
「検証の目的」「検証の対象」「検証の必要性」等を十分考えた上で、開発を検討すべきです。
プロトタイプに要件を盛り込みすぎてしまう
せっかく開発するのであれば、あれもこれも・・・といった思いから、完成形とほとんど変わらない要件をプロトタイプに盛り込みすぎてしまうケースも多くみられます。
プロトタイプ開発の目的を明確にして、本当に検証が必要なことが実施できる機能に絞り込むべきです。
まとめ
プロトタイプ開発は「検証内容の定義」「プロトタイプの要件定義」「プロトタイプの設計」「プロトタイプ開発」「評価・判断」の5つのステップで進めていきます。
その際、プロトタイプは捨てるのか、そのまま完成品へと成長させるのか?を決めておくことが非常に重要です。
また、プロトタイプ開発そのものが目的になってしまうことや、要件を盛り込みすぎて従来の開発と変わらない状態になってしまうこともあるので注意が必要です。
あくまで、評価・検証のためのものであることを意識し、必要最小限のものをスピーディーに作り上げることを心がけると良いでしょう。
プロトタイプ開発をさらに加速させることができるのが「ノーコード開発」です。
ノーコード開発ツールを使えば、開発における「コードを書く」という工程が削減できるため、従来の開発よりも速く、簡単に、コストを抑えてアプリケーションを作る事ができます。
また、提供されいてる機能を活用して、仕様や機能を柔軟に変更できるため、開発・評価・検証を繰り返すプロトタイプ開発には適したツールだといえますので、一度検討してみてはいかがでしょうか?
プロトタイプ開発やノーコードはNCDCにご相談ください
NCDCでは、独自のメソッドを使った新規事業立ち上げサポート、UXデザインを重視しながらのプロダクト開発、リーン・スタートアップ、アジャイル開発の経験も豊富なため、新規事業開発プロジェクトのプロトタイプ開発を包括的にサポートする事ができます。
また、ノーコード開発ツール選定などもお手伝い可能です。
新規事業開発、プロトタイプ検証、MVPの検証をご検討の際にはぜひご相談ください。